ブログ
Blog
パワハラ研修で気づいた「指導」の真髄:心構えが組織を変える
ハラスメント
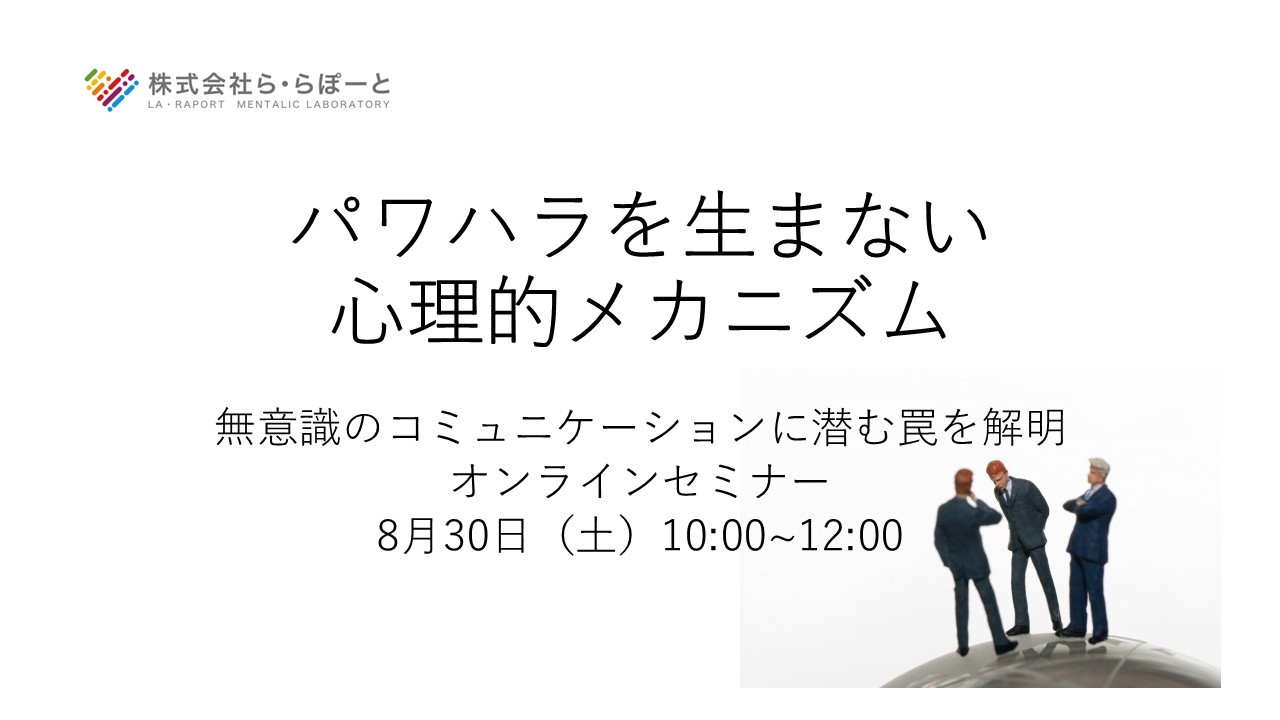
パワハラ研修で気づいた「指導」の真髄:心構えが組織を変える
先日、中小企業から大企業まで、様々な企業でパワハラ防止研修を実施しました。その中で、ある参加者の方から受けた質問が、私に改めて「指導」の本質を深く考えさせてくれました。「業務上必要な会社の教育的指導」と、あわれみサポートの違いが曖昧だ」という、切実な問いかけでした。
私たちは日々の業務の中で、「指導」という言葉を当たり前のように使います。しかし、その「指導」が、いつの間にか部下を追い詰める「パワハラ」に変わりかねない危険性をはらんでいることを、多くの人が認識しています。この危険なラインをどこに引くべきか。その答えは、単なるマニュアルやルールブックの中にあるのではなく、指導者自身の「心の持ち方」にあるのだと、私はこの研修を通じて確信しました。
「業務上必要な指導」は「共に成長する喜び」
私は、この質問に対し、「業務上必要な会社の教育的指導は、会社の一員として誇りを持ち、上司または先輩として、部下や新人を尊重しながら指導し、その成長を心から喜ぶ、そういう意識です」と答えました。
この考え方では、指導する側とされる側は、一方的に教える・教えられる関係ではありません。共に目標に向かって進む、対等なチームメイトです。
例えば、新人社員が初めて任されたプレゼンテーションで、これまで練習してきた成果を発揮し、自信をもって発表できたとします。この時、会社の教育的指導の心構えを持つ上司は、発表の成功を自分のことのように喜びます。
「〇〇さんのプレゼン、とても分かりやすかったよ!特にグラフを使った説明の仕方が格段に上手くなったね。今回の成功、本当に嬉しいよ。」
このような言葉をかけられた部下は、「自分の努力を認めてもらえた」「上司が自分の成長を喜んでくれている」と感じ、大きな達成感と自己肯定感を得ます。すると、次の課題にも前向きに取り組むモチベーションが自然と湧いてきます。それは、働きがいにもつながります。
そして、このやり取りが繰り返されることで、指導者と部下の間に強固な信頼関係が築かれます。信頼関係は、失敗した時にも力を発揮します。たとえミスを犯しても、「この上司は、自分の成長を願ってくれているから、きっと次につながるアドバイスをくれるはずだ」と安心して相談できます。このようにして、指導は単なる業務の伝達ではなく、互いの成長を促すポジティブなコミュニケーションへと昇華していくのです。
「あわれみサポート」がもたらす深い溝
一方、私が「あわれみサポート」と表現した指導姿勢は、「仕事ができない社員を育ててあげなければならない」という、ある種の憐憫や同情から生まれます。
この意識には、知らず知らずのうちに「上から目線」が入り込んでいます。指導者は、部下の未熟さを前提として関わるため、「教えてあげたことができて当然」「成長して当たり前」という感覚に陥りがちです。
同じ新人社員のプレゼンテーションの例で考えてみましょう。「あわれみサポート」の心構えを持つ上司は、部下がプレゼンで成功しても、心からの喜びを感じることが難しいかもしれません。
「まあ、当たり前だよね。これくらいできてくれないと困るから。」
このような言葉、あるいは態度は、部下の努力や成長を軽視し、感謝や労いの気持ちを伝えにくくさせます。部下は「自分の努力は認められない」「この人には何をしても褒めてもらえない」と感じ、モチベーションは下がる一方です。働きがいも低下します
さらに、この心構えが持つ一番の危険性は、部下が成長した時に現れます。指導者側の「私が育ててあげた」という気持ちが強いほど、成長した部下を「自分のコントロールを離れていく存在」だと無意識に感じてしまうことがあります。すると、部下の活躍を素直に喜べず、どこか「疎ましい」という感情すら芽生えてしまう。この段階に至ると、指導はもはや育成ではなく、関係性を悪化させる要因となります。信頼関係は崩壊し、互いに不信感を抱くようになり、それはやがてパワハラへと発展しかねません。
健全な指導のカギは「心の持ち方」
今回の研修を通じて、私は改めて、健全な指導とパワハラの境界線は、個々の行動の良し悪しだけでは判断できないことを痛感しました。
- 教育的指導: 相手の成長を心から願い、喜びを共有する姿勢
- あわれみサポート: 相手を「未熟な存在」と見なし、一方的に「してあげる」姿勢
この二つの根本的な違いは、指導者自身の「心の持ち方」にあります。パワハラ防止研修は、単に法律やルールを学ぶ場ではありません。それは、上司と部下が互いに尊重し合い、共に成長していくためのコミュニケーションのあり方、そして何より、自分自身の「心の持ち方」を見つめ直す、貴重な機会なのだと確信しました。
私たちは、部下や新人を「育てる」のではなく、「共に働く仲間」として、その成長を心から喜び、応援する姿勢を持つべきです。その意識こそが、組織全体のパフォーマンスを向上させ、健全で活気ある職場環境を築くための、何よりも重要なカギとなるのです。
【研修のご案内】健康経営を実現する各種研修のご案内
・パワハラの研修
・コミュニケーションの型
・大人の発達障がいや能力特性
・メンタルヘルスケア
・アンガーマネジメント
その他
研修によって、健全な人間関係が育まれ、ストレスの少ない生産性の高い職場環境が実現します。これは、まさに健康経営を推進し、企業の持続的な成長を確かなものにするための、重要な一歩となるでしょう。
研修のお問合せはこちらhttps://laraport.jp/eap/eap-contact/
※これらの研修は一般的な研修とは違い、SSD(Spinal signal Decoding学会)研究会の学びをもとに、実際のカウンセリングやコミュニケーションのワークでの検証を基に開発しています。

 TEL.
TEL.