ブログ
Blog
パワハラは「無意識のコミュニケーション」から生まれる?その心理的メカニズムと解決策を探る研修のご案内
研修
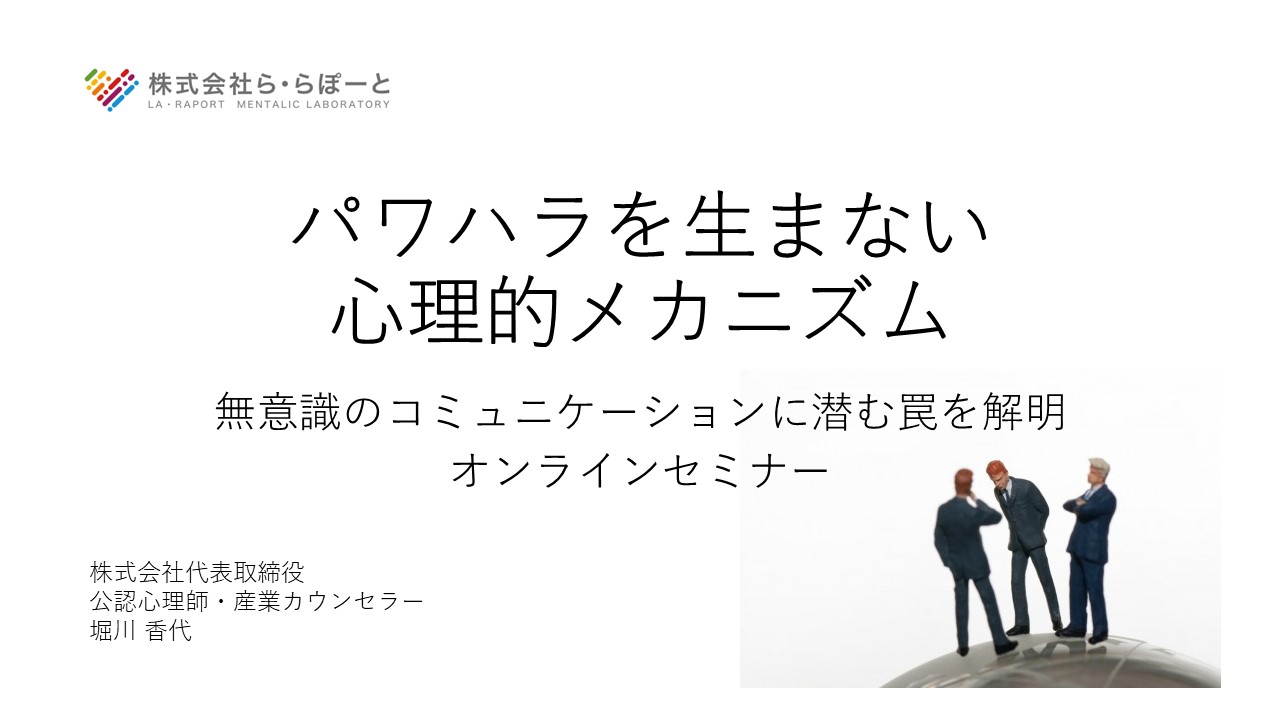
パワハラは「無意識のコミュニケーション」から生まれる?その心理的メカニズムと解決策を探る
職場でこんな悩みを抱えていませんか?
- よかれと思って指導したのに、部下は委縮してしまった
- ハラスメント対策はしているのに、問題が潜在化しているように感じる
- 上司と部下の間で認識のズレが大きく、話し合いがうまくいかない
- 期待していた若手社員が、突然休職したり早期退職したりしてしまう
もし一つでも心当たりがあるなら、それは個人の性格や資質の問題ではなく、もしかしたら無意識のコミュニケーションの歪みから生じているのかもしれません。
今回は、パワハラが生まれる「心理的メカニズム」を解明し、健全で生産的な職場環境を築くためのヒントを学ぶオンラインセミナー「パワハラを生まない心理的メカニズム」についてご紹介します。
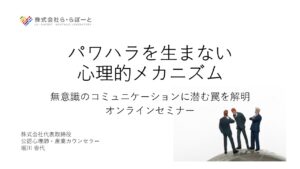
研修の背景にある、現代の職場が抱える課題
パワハラ問題は、多くの企業が直面する大きな課題です。2020年6月には、大企業でパワハラ対策が義務化され、2022年4月からは中小企業にも拡大されました 。しかし、表面的な対策だけでは根本的な解決には至らず、問題が潜在化しやすいのが現状です 。
特に深刻なのは、加害者と被害者の間で認識の大きなズレがあることです 。指導のつもりで発した「良かれと思って」の行動が、相手には「叱責」や「問い詰め」と受け取られ、部下が疲弊してしまうケースが多く見られます 。
また、ハラスメントは上司から部下への一方的なものだけではありません。同僚間や、時には部下から上司へのハラスメントも含まれます 。
こうした問題の根源は、実は私たちの**無意識の「コミュニケーションの型」**にあると、このセミナーは指摘しています 。不適切なコミュニケーションが、知らず知らずのうちに心理的な構図を作り出し、パワハラへと発展してしまうのです 。
パワハラを生む2つの「無意識のコミュニケーションの罠」
このセミナーでは、パワハラにつながる2つの具体的なコミュニケーションの型を提示し、その心理的メカニズムを深く掘り下げていきます 。
1. 「感情を伴わない状況説明」の罠
困った状況を相談する際、私たちはつい感情を抜きにして、事実だけを説明しがちです。たとえば、「〜のやり方が分からないので、教えてください」といった伝え方です 。
これを受け取った側は、相手が「分からない」という状況を解決しようと、責任感からあれこれとアドバイスをしてしまうことがあります 。しかし、このやり方では、相談者が本当に困っている**「不安」という感情的な問題**に焦点が当たらず、不必要な情報ばかりでかえって混乱させてしまいます 。
結果として、相談者は「冷たい」「突き放された」と感じたり、理詰めで攻撃されているように感じたりし、「自分はやはりダメな人間だ」と不安を募らせてしまうのです 。
2. 「あわれみサポート・価値観の押し付け」の罠
もう一つの罠は、無意識のうちに
主従関係が形成されてしまうことです 。
「自分の方が相手より立場が上だ」「自分の価値観こそが正しい」といった意識が働くと、相手を「かわいそうな人」「未熟な人」と見なし、一方的にサポートや自分の価値観を押し付けてしまうことがあります 。
この関係性の中で、支配する側は、自分の指示や命令に従わない相手に対して大きなストレスを感じ、それがパワハラへと発展します 。一方、支配される側は、「自分はダメな人間だから従うべきだ」という心理状態に陥り、自信を失い、常に誰かに依存しなければ不安でいられなくなってしまいます 。
これらの罠に陥らないためには、表面的な行動や性格の問題として片付けるのではなく、その背景にある「無意識のコミュニケーションの歪み」を心理学的に解明し、深く理解することが不可欠です 。
健全な職場を築くための3つの実践的な解決策
このセミナーは、問題の根源を明らかにするだけでなく、明日から実践できる具体的な解決策も提供します 。
1. 「不安」を適切に言語化する
相談する側は、単に状況を説明するだけでなく、自分の**「不安」な気持ちを現在形で言語化する**ことが重要です 。
たとえば、「機械の操作が苦手で、どうしたらいいか分からず不安です」と伝えることで、相手は「不安」という感情を理解し、「サポート&見守りモード」に切り替わりやすくなります 。その結果、建設的なサポートを引き出すことができ、お互いに安心して働ける関係が築けます 。
2. 「合意形成」を実践する
健全で対等な人間関係を維持するためには、「合意形成」が不可欠です 。
これは、単に相手の意見に合わせるのではなく、
お互いの感情や条件を現在形で伝え合い、対等な立場で話し合い、合意を得ることを指します 。お互いが同じ価値の条件を交換し合うことで、一方的な支配や依存の関係を生まない健全な関係を築くことができます 。
3. 自分のコミュニケーションの「型」を意識する
まずは、自分がどのようなコミュニケーションの「型」を持っているかを意識することが第一歩です 。
- 困った状況を説明する時、感情を伴わず、事実だけを伝えていないか?
- 相手にアドバイスをする時、「良かれと思って」一方的に価値観を押し付けていないか?
このように自分自身を振り返ることで、無意識のうちに生じていたコミュニケーションの歪みに気づくことができます。
まとめ
このセミナーは、パワハラの根本原因を「無意識のコミュニケーションの歪み」と捉え、その心理的メカニズムを深く理解することを目的としています 。単なる「行動」や「性格」の問題に留まらず、心理学的なアプローチで根本原因に迫るのが特徴です 。
このセミナーに参加すれば、パワハラを未然に防ぎ、健全で生産性の高い職場環境を築くための具体的なコミュニケーションの型を学ぶことができるでしょう 。
パワハラのない、みんなが安心して働ける職場を目指して、第一歩を踏み出してみませんか?
セミナー詳細
- タイトル: パワハラを生まない心理的メカニズム~無意識のコミュニケーションに潜む罠を解明~
- 講師: 堀川 香代(株式会社ら・らぽーと 代表取締役、公認心理師・産業カウンセラー)
- 形式: 対面、オンライン
お問い合わせはこちら

 TEL.
TEL.